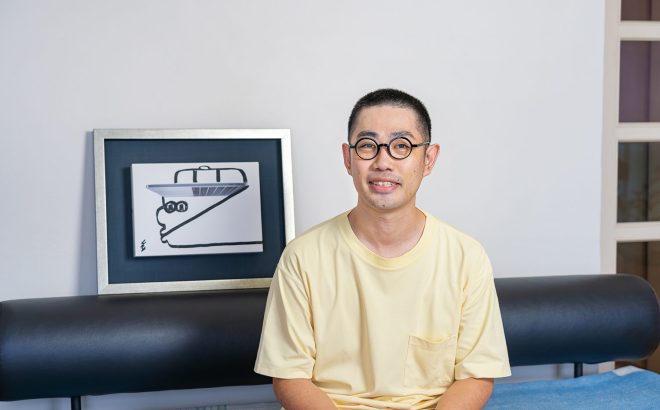鮮やかな色彩に、迫力ある造形が印象的なねぶた。そのねぶたを間近に見ることができるねぶた祭りは、毎年多くの来場者で盛り上がる青森の夏を彩る大切な存在です。
北村麻子(きたむらあさこ)さんは、ねぶた師史上初の女性ねぶた師。六代目ねぶた名人である父・北村隆(きたむらたかし)さんの背中を見て育ち、2012年にねぶた師としてデビューしました。今回は、北村さんがねぶた師を志した理由、デビューまでの道のりについて、株式会社クリエイターズマッチ代表取締役の呉京樹(ごけいじゅ)がお話を伺いました。
初めて出会えた「やりたいこと」
呉:北村さんは、ねぶた師になられる前に、いろいろと悩まれながら仕事を変えてこられたそうですね。どのようなお仕事をされてこられたのでしょうか。
北村:最初は神社の巫女さんですね。その後、販売の仕事や事務の仕事をいくつか経験してきましたが、どの仕事も長続きせず……。責任を持って、やりがいを感じて続けられる仕事に出会えない状態が続きました。
呉:何かやりたいことがあったというよりは、いろいろ経験されてきたという感じだったのですね。
北村:そうですね。絵を描くことは小さいころから好きだったんです。でも、絵を描くことを生業として生活していくことは頭にはなく、まず無理だろうと思っていたんです。だからこそ現実的な仕事を選んできたのですが、20代半ばになったころ、「そろそろ本腰を入れて、自分がどう生きていくのかを決めなきゃいけない」と感じました。1回きりの人生なのだから、やっぱり好きなこと、やりたいことを仕事にしようと考えるようになり、デザイン関係や絵を描く仕事を目指そうと思ったんです。ただ、その時点では、ねぶた師になるなんて全然想像していませんでした。
呉:北村さんがねぶた師を目指すきっかけになったエピソードはありますか。
北村:ねぶたがいかに自分の中で大きな存在だったかをあらためて思い知ることになったのは、父が足を悪くしたことがきっかけでした。小さいころから生活の中に当たり前のようにあったねぶたが、なくなってしまうのかもしれないと思ったときに気付かされました。
呉:青森に根付く文化そのものですよね。歴史や文化を守る意識が強く働いて「そのために自分ができることは何か」と考えた結果、ねぶた師を志したのでしょうか。
北村:最初からそこまで大きくは考えていませんでした。私は父が大好きで、幼いころから尊敬していたんです。ねぶたを作る父を誇りにも感じていました。
おっしゃる通り、ねぶたは青森の文化で、青森の人たちはねぶた師に対して敬意を払ってくれるんですよ。「お父さん、ねぶた師ですごいね」「いい仕事をしてるね」と声をかけてくださって。親が何も言わなくとも、父がやっていることは素晴らしいことなんだと誇りに思っていた部分がありました。そうした背景もあり、やっぱり自分が守っていきたいと思うようになったんです。
呉:本当にすごい方ですよね。ただ、あれだけ素晴らしいお父様と同じ業界に入るのは、恐怖やプレッシャーもあったのではないでしょうか。
北村:よく聞かれるのですが、実はまったく感じてはいません。というのも、私は小さいころからやりたいこととか、将来なりたいものが一切なく、趣味すらもなかったんですよ。それがずっとコンプレックスでした。そんな私が生まれて初めて「これをやりたい」と思えたのがねぶた師だったんです。
夢や目標を初めて持てたことが本当にうれしくて、それだけで幸せでした。だから、プレッシャーや恐怖心はまったく関係なく、とにかくその世界に飛び込むんだ、この気持ちだけは絶対に手放しちゃダメだと強く思いました。うれしくて楽しくてしょうがなかったですね。

呉:いやあ、素敵ですね。プレッシャーがまったくなかったというのは強い方だなとも思いました。特に影響を受けたお父様の作品はありますか。
北村:2007年の『聖人聖徳太子』 ですね。自分の人生が変わったと言えるほど、私にとって大きな存在です。今までのねぶたにはないような構図と色遣いが特徴的でした。それまでのねぶたは白熱球が9割を占め、刀など青系の部分にだけ蛍光灯を使うことが一般的だったのですが、聖人聖徳太子は蛍光灯を5割も取り入れ、これまでにない光の使い方だったんです。そこに強く影響を受けましたし、聖人聖徳太子の神々しさや見た目の美しさにも心を奪われました。
あとは、作品の背景も大きかったです。父がこの作品を作るまでにどんな数年間をどんな思いで過ごしてきたのかも見てきました。順風満帆な人生を歩んできた人が作る作品と、どん底を経験し、そこから這い上がって辿り着いた作品とでは、やはり全然違うものがあると思うんです。父の苦しんできた姿も見てきたことが作品の素晴らしさ、美しさと相まって、「自分もやろう」という気持ちになりました。
呉:僕も初めて生で見ましたが、本当に色がきれいでした。北村さんの作品も、色遣いのきれいさに言及されることが多いと感じているのですが、それもお父様の作品からの影響があるのでしょうか。
北村:そうですね。今年の作品『役小角(えんのおづぬ)』の雲の表現は、実は聖人聖徳太子の着色方法を少し意識した部分がありました。でも、まだまだ父には届かないなあと思いましたけれども。
両親の言葉に背を押され、
史上最速デビューへ
呉:ねぶた師を志されてから、北村さんはデビューまでが非常に早かったそうですね。わずか4年で制作依頼が来たと。当時はどう感じられたのでしょうか。
北村:「いや、無理です」と(笑)。本来であれば、10年ほど修業したころに制作依頼がきて、「ぜひ!」と飛びつくものなのですが、私の場合はその半分も満たない4年ほどだったので。中途半端な作品は作りたくないですし、もう少し基礎的なことを学んでからデビューさせてほしいという気持ちもあって、「ちょっと無理だな」と感じました。
呉:実際にお断りされたのですか。
北村:はい。私からもお断りしましたし、父も「3年は早い」と断っていました。
呉:通常は10年と言われているなかで、それはそうなりますよね。でも、結果的にはお受けになった。それはどういう心境の変化があったのでしょうか。
北村:依頼してくださった青森市民ねぶた実行委員会の会長さんから、「あと3年必要なんだったら、3年大型ねぶたを作りながら勉強すればいい」と言われたんです。「そんな無茶苦茶な」と思いましたが、父もその言葉を受けて考え直したようで。
ある日、父が「自分はおまえの年ごろに、実力はあったけれども機会に恵まれず、デビューできずにずっと悔しい想いをしてきた。チャンスはなかなかやってこないものなのだから、やってみたらどうだ」と言ってくれました。そこで、「そうか」と思いはしたのですが、まだ決心はつきませんでした。
そんな私の背を押したのは、その後に母から言われた「何年修業を積んだって、誰だって最初は初めてなんだよ」という言葉でした。自分のなかで腑に落ちたところがあって、「やろう」と思えたんです。
呉:なるほど。その会長さんもユニークですね。作りながら覚えろということですか。
北村:はい。今となっては、あのタイミングでデビューして良かったなと思います。あのとき、声をかけてくださったことに感謝しています。すでに亡くなられてしまいましたが、私にとっては恩人です。
呉:そうでしたか。お母様のお言葉も心に響きました。「誰でも最初は初めて」は、まさにどの仕事にも言えることだなと思います。

早期の大賞受賞がプレッシャーに
呉:北村さんは、ねぶた師になられてから、数々の受賞をされていますが、その裏には苦労や葛藤もあったのではないかと思います。いかがでしょうか。
北村:そうですね、いろいろありました。まずはデビューの年、いきなり優秀製作者賞をいただいたことで、ある意味で僻みみたいなものもすごく受けまして。「女だから贔屓されている」とか「本当は父親が作っているんじゃないか」など、さまざまなことを言われました。でも、そこに関してはあまり気にはしていませんでしたね。いずれわかることじゃないですか。父親に作らせていたとして、そう長く続くようなことではないですし。自分が誰にも何も言わせないぐらい良い作品を作れば、自然とそういう声はなくなるのだろうと確信していました。
修業時代も、スタッフの方々に受け入れてもらえないことがありました。でも、たとえ1年で変わらなかったとしても、2年、3年、4年と本気でねぶたに向き合って修業すれば、必ず周りに伝わり状況は変わっていくものなんですよね。そうした経験をしてきたので、デビュー時も、きっとこの状況は誠実に作品に向き合っていれば変わるという確信があって、焦りや苦しみはなかったんです。
呉:いやあ、すごい。強い方ですね。
北村:根底に「生まれて初めて本当にやりたいことに出会った」という想いがあったことが大きいのだと思います。
呉:周りの声に左右されるよりも、純粋に「楽しい」という気持ちが後押しになっているのでしょうね。
北村:そうですね。その後に苦しんだのは6年目、最高賞であるねぶた大賞を受賞したあとです。6年目での大賞の受賞はおそらく歴代最速といえるスピードなんです。もちろん、いずれは大賞を取れるねぶた師になりたいとは思っていましたが、最低でも10年以上かかる覚悟をしていたので、まさか6年目でいただけるとは思ってもいなくて。そこで初めてプレッシャーを感じました。次の年は、何を作ればいいのかわからなくなってしまって。苦しいと思ったのは、その時が初めてでしたね。
呉:最優秀賞を取ってしまったわけですもんね。だからといって次の目標を見失うわけではないとは思いますけれども、重いですよね。
北村:そうなんです、あまりにも重すぎました。さらに周りから「二連覇だ!」と期待の声が上がるので、余計に苦しかったですね。
呉:周りは好き勝手言いますからね。受賞翌年、テーマ選びも難航したのでしょうか。
北村:そうですね、スムーズにはいかなかったです。自分のどこが評価されたのかもわからず、何を作ればいいのかが見えなかったんです。
呉:それでも、次のねぶたは待ってくれない。作らなければならないわけですが、どう乗り越えられたのでしょうか。
北村:たぶん、乗り越えられなかったですね。迷いがそのまま作品に出てしまって、その年は終わったように思います。迷走してしまいましたね。
呉:その翌年は、迷いをリセットできたのでしょうか。
北村:そうですね。少し力が抜けて、「もう自由に作ろう」と思って。受賞の翌年は、かなり力が入っていて、「何か新しいことをやってやろう」と、すごく細かく造形を作り、やったことのない構図に挑戦してみたんです。でも、その次の年は「1回原点に立ち返ろう」と思って、構図もスタンダードな、すごくシンプルなものにしました。「色だけで新しい表現ができるかもしれない」と思い、色遣いだけは自分の感性に従って制作したところ、良い評価をいただくことができました。

(提供:北村麻子さん)
ー おわりに ー
業界初の女性ねぶた師と、ただでさえ注目を集める存在でありながら、いち早いデビュー、受賞と華々しい実績を残した北村さん。迷い、葛藤がありながらも前進し続けられたのは「初めて見つかったやりたいことだから」という強い想いでした。第2回「賞がすべてではない」では、コロナ禍の経験で変化したねぶたへの想い、2025年に制作した作品について伺います。
PROFILE
北村麻子(きたむらあさこ)
ねぶた師
1982年10月生まれ。父親であり、数々の功績を遺すねぶた師の第一人者、六代目ねぶた名人の北村隆に師事し、2012年に女性初のねぶた師としてデビュー。デビュー作「琢鹿(たくろく)の戦い」が優秀制作者賞を受賞、6年目の作品「紅葉狩」で最優秀制作者賞、ねぶた大賞を受賞するなど、数々の賞に選ばれ、多くのメディアに取り上げられる。近年では、百貨店や企業とのコラボレーション作品の制作などにも精力的に取り組み、ねぶたの魅力を国内外に発信している。
ねぶた師 北村麻子 公式サイト:https://asako-kitamura.com/