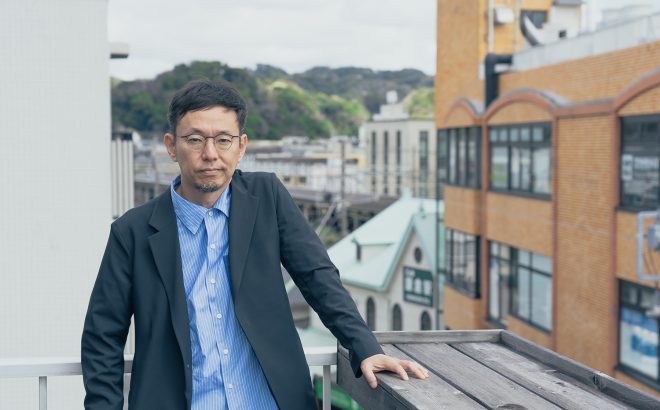絶景とは何でしょうか。どのように向き合えば良いのでしょうか。詩歩(しほ)さんへのインタビューの最終回。その答えを教えてもらいました。
ストーリーで深まる絶景の感じ方
私の中では絶景の定義が2つあります。1つは見た目の美しさ、景観の美しさ。もう1つはストーリー(物語)の有無を基準としています。わざわざ時間とお金をかけてその場所に行く、それだけの理由があるのか。そこの場所にしかない物語が、その景色の裏側に広がっているということを重要視しています。例えば最近よくある、いわゆるインスタ映えみたいなものはほとんど人工的に作ることができます。そこの場所じゃなくても、他の場所でも再現性があると思うんです。だから、その土地にしかないような物語があったり、その地形が地球の歴史でできていたり、そこにわざわざ行かないと見えないようなオンリーワンの価値がある場所を絶景の条件にしています。私の中の絶景はインスタ映えとはちょっと違うかなと思っています。
昔から歴史は好きだったのですが、世界史は未履修だったこともあり、知識としてはあんまりない状態で海外旅行をしていました。2014年にひとり旅で初めてトルコに行き、カッパドキアでは乗りたかった気球に乗りました。上空から眺めて、景色すごい、洞窟すごい、と思ったんです。また、洞窟の地下都市が有名ということで、見て回りました。けれども正直、なぜ地下都市があるのか、なぜそれが世界遺産ですごいのか、ということはあまり理解ができませんでした。英語ガイドは聞いていましたが、なんか洞窟あるね、くらいの薄っぺらい感じで帰国をしてしまいました。

それが新型コロナウイルスの感染流行をきっかけとして、ちょっと何かを勉強しようと思い、2021年に世界遺産検定の1級という資格を取得したんです。世界史を本当に0からいろいろと勉強しましたが、その時にカッパドキアの洞窟都市というのはすごく歴史的な価値があって、物語があるということを初めて知りました。迫害されたキリスト教徒たちが隠れ住むために自分たちで掘って、地下7階、8階と住む場所をどんどんと拡大していき、それが今もなお残っているんです。キリスト教徒だから、洞窟の中には教会のスペースがあり、キリスト教の壁画が残されていることを知りました。「キリスト教の絵なんてあったっけ?」と思って、旅行写真のフォルダを遡ってみたら、実は撮っていたんですよ。当時は何も知らないまま、本当になんとなく解説されたから、写真を撮った。その程度でしたが、いざ勉強をしてみると、こんな歴史があったんだって。それを知ってから旅行をしていたら、実際に感じるものは違ったんだろうなと思いました。
去年2023年12月に2回目のトルコ旅行をして、同じ場所を巡ってきました。1回目は「ふーん、洞窟すごいね」でしたが、今回は「当時の人は本当に辛い気持ちでここを掘っていたんだな」という感情を抱き、旅行をすることができました。「感じ方」がもう2倍も3倍も深くなり、理解すること、楽しむことができたんです。やはり、裏側のストーリーを知ってから、その土地に行かなければいけないと感じました。
ちょっと話が逸れるかもしれませんが、日本の高校では2022年度から世界史Aと日本史Aを統合した「歴史総合」が新たな必須科目になりました。これまで必須だった世界史Aもしくは世界史Bは必修科目ではないんです。世界史の知識が浅いまま、グローバル、グローバルと言われて、グローバルに押し出されてしまう子どもたちが増えてしまうことに危機感を覚えています。世界史はもっと知るべきだし、知るとやはり楽しいですよ。世界の歴史を知ることができる機会がこれから増えたらいいのにとすごく思っています。
本質的な課題と向き合う
この10年、風景に注目を続けていると自然環境の変化をとても感じますし、地球の気候変動の早さはひしひしと感じるものがあります。日本の桜の開花なども予測がつかなくなり、もう綺麗に咲かなくなってしまうかもしれません。秋の紅葉も夏が暑すぎると色づかなくなってしまいます。北海道の流氷は着岸時期がどんどんと遅くなっていて、もしかしたら、もう来なくなってしまうかもしれません。ちょっと初心に立ち返るではないですけれど、環境問題に取り組みたいと思っています。
それ以外にも、最近課題だと感じていることがあります。SNSには良い面も悪い面もありますが、一気に情報が広まってしまうがゆえ、現地の受け入れ体制が整わないままに急に人が殺到するオーバーツーリズムが起きています。情報発信のあり方を考えなきゃいけないということを強く思っています。
昨年の秋に栃木県の日光にある霧降高原を訪れましたが、ちょうど1年前ぐらいからTikTokなどで10代後半から20代の世代を中心に急激にバズっていたんです。1445段の階段が真っすぐに山の上の展望台に繋がっていて、「天空の回廊」と呼ばれています。真っ暗なうちから登ると、早朝には雲海が眼下に広がります。そういう光景がいわゆるエモいということで、流行っているんですね。1445段を踏破するということもストーリー的に映えて、さらに雲海がすごい綺麗ということで、新型コロナの影響で旅行できなかったような人が殺到しているんです。

私が行ったのは10月頃でしたが、寒い地域なので雪が降り始めていたんですね。ところが、「SNSでバズったから」という理由だけで来るような人たちは事前情報を十分に調べておらず、車はスタッドレスタイヤを履いていません。1445段の階段には雪が積もり、凍結しているのですが、そんな人たちの足元はスニーカー。滑って、本当に危ないんです。霧降高原にはニッコウキスゲという貴重な植物もありますが、ゴミを捨てたり、車を横断歩道の上に路上駐車したり、マナーが良くない人たちも多い。ゴミ拾いをしている地元の人がSNSで、「この数カ月は本当にひどい。困っています」と書き込んでいました。早朝の時間帯は誰も管理する人がいないので、注意をする人もいなかったのでしょう。
その土地へのリスペクトがないからこそ、そういう迷惑な行動をしてしまうのだと思います。地域の景色は地域の人たちが守ってきたからこそ、外から来た人たちは楽しむことができる。地域に対する愛情やリスペクトを持ち、観光をする人が増えてほしいなと強く感じます。啓発の看板を立てるみたいなシンプルなことで改善されるわけではないので、どうしたらいいんだろうなっていうことをちょっとモヤモヤと考えています。
カメラを趣味とする人が殺到することで、写真撮影を巡るトラブルや事件もたくさん起こっています。例えば、電車が好きすぎるがゆえ、入ってはいけないところに入って、電車を止めてしまう。田んぼに水が張っているところを撮るために勝手に他人の田んぼに水を張ってしまう。この木は邪魔だからと勝手に他人の庭の木を切ってしまう。SNSでバズりたい、自分だけいい写真を撮りたいというエゴが、地域や自然への愛情を上回ってしまうことで、そういったトラブルに繋がることがあるんです。すると、その場所は立ち入り禁止になり、見ることができなくなるという元も子もない結果を招いてしまいます。私もSNSで情報を発信する側ではあるので、なんとか解決しなければとの危機感をすごく感じています。
そこにしかない景色を楽しむ
10年目を迎えて、仕事をいろいろと選ばせてもらえる立場になったことはありがたいですね。やる、やらないとの最終的な判断基準は、自分自身が旅を楽しめるかどうか。旅に楽しみを感じなければ結局は撮った写真に「楽しくない」という感じがにじみ出てしまうのではと思っています。本当に楽しいと思えたものしか、発信はしない。そういうところは守っていきたいと思って、活動をしています。旅好きとして、旅とは楽しめるものだということを忘れないようにやっていきたいです。
いわゆるインフルエンサー・マーケティングやPR投稿のご依頼が増えてきています。いいなと思っていなくても、お金をもらえれば投稿する方も中にはいらっしゃると思いますが、それは正直、残念だと感じています。私はインフルエンサーではなく、あくまでプロデューサー。お金をもらっていても、もらっていなくても、本当にいいと思ったものだけを紹介をしていきます。
日本の魅力はまだまだ知られるべきだと思っています。今後の目標としては、海外に向け、日本の魅力を紹介していきたいです。私のフォロワーさんは日本人が8割ぐらいなので。そのために2016年頃から、英語の勉強を本格的に始め、実は短期留学をしていた時期もありました。具体的な行動は全然起こせていないのですが、Instagramの発信などには英語のキャプションをつけています。日本についてはまだ知られていないことが多く、そんな日本の魅力を伝えたいと常々思っています。

本当に日本って素晴らしい国だなと思っています。山もあれば海もあり、川もあれば湖もある。南北に長いために気温差があり、四季があるために1年を通していろいろな景色を見ることができます。こんな小さな国で、こんな豊かな国は他にないと思うんです。それぞれの地域でしか見られない景色というものが絶対、それぞれの地域に眠っています。だから、自分が住んでいる地域で、普段は外出しない夜の時間にちょっと外に出てみると、天の川がバーっと空を横切り、美しく輝いていたりします。ちょっと早起きをすると、その時期だけはちょうど岩の間から、すごく綺麗な太陽を見ることができるかもしれません。暮らしている場所でも少し視点を変えてみると、新しい魅力は見つかりやすいものです。暮らしている場所の新しい魅力をぜひ、皆さん自身の目線で見つけてください。それを世界中の人に紹介していくことで、地域の未来ももっと見えてくるんじゃないかと感じています。
ー おわりに ー
詩歩さんは昨秋、日本で一番早い紅葉を撮影するため、標高2000メートル級の北海道・旭岳を目指したそうです。忙しい身とあって、スケジュールに余裕は作れません。ところが、気候変動の影響で、昔に比べると絶景の撮影に最適な日時を予測することが難しい。ぎりぎりまで天気図とにらめっこし、直前に決断したと言います。
「風景に注目を続けてきて、自然環境の変化をとても感じるようになりました」と、詩歩さんは振り返ります。一方の私たちはSNSなどで注目を浴びたいがため、記念撮影のための風景を探してはいないでしょうか。一過性の興味本位ではなく、きちんと自然に接すること、見守ることの大切さを詩歩さんは教えてくれます。
PROFILE
詩歩(しほ)
絶景プロデューサー
静岡県「ふじのくに観光公使」、静岡県浜松市「やらまいか大使」、愛媛県「愛媛・伊予観光大使」
静岡県浜松市出身。早稲田大学人間科学部卒。
広告代理店の新人研修時に「絶景」に着目し、制作したFacebookページが人気を呼ぶ。
著書『死ぬまでに行きたい! 世界の絶景』はシリーズ累計63万部を突破した。
2014年に独立。自治体の地域振興、旅行商品のアドバイザーなどを務めている。
SNSのフォロワーは100万人を超える。
トレードマークはニット帽で、遺跡好き。
公式サイト「Shiho and...」:https://shiho.me/