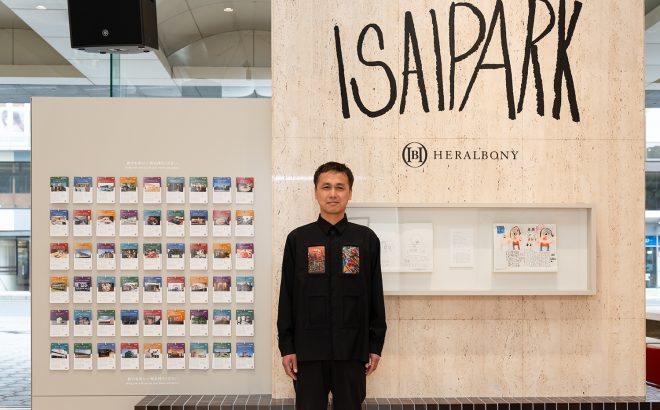岡山県の西北端に位置する新庄村は、人口約800人、370世帯の小さな村です。村政が施行された明治5年より、一度も合併することなく存続し続け、平成の大合併が話題となった際も、新庄村として存続させていく道を選びました。そんな新庄村で、1990年より4期にわたり村長を務め、8年のブランクを経て現在は3期目を務める小倉博俊(おぐらひろとし)さんに、新庄村での取り組み、小規模な自治体が生き残る術についてお話を伺いました。
合併はしない。
自主自立を掲げた村づくり
新庄村は、岡山県の北西部に位置する小さな村です。この村で、私は28年間、村長として村づくりを進めてまいりました。
この間、私が変わらず大切にしてきたのは、「小さくても自主自立の村を目指す」こと。これは2002年に新庄村定例議会で決議された新庄村宣言です。背景には、この当時あった「平成の大合併」の流れがあります。あちこちの小規模な自治体がそうであったように、当時の新庄村にも「小さな村なのだから、周りと合併したほうがいい」という誘いがありました。合併すれば財政的な負担が軽減されるというのが賛成派の主な意見で、国としても自治体数が合併により減ると財政の効率化が図れるという狙いがあったのです。
しかし、私はすぐに「では、我々も平成の合併号という名のバスに乗ろう」という判断は下しませんでした。いずれ合併の波がやってくると感じていた私は、「まずはメリット、デメリットを知ろう」と調査を3年ほどかけて進めていたのです。チームを組んで視察に行ったり、合併推進派、慎重派それぞれの先生の講演に足を運んだり。合併により借り入れることができる地方債、合併特例債のシミュレーションも行い、そうしたメリット、デメリットをまとめた冊子を作りました。
そうして、いざ合併の世論が高まってきたタイミングで、その冊子を持って村民の元に出向いたのです。意見交換会を重ねるうちに、「自分ごと」として関心を持つ村民が次第に増えていったように感じます。
この「村民の意見を聞く」というのは、村長にはじめて就任したときから心がけていることです。「村社会」という言葉がありますが、新庄村も良くも悪くもその特徴を持っていると感じています。地域の結びつきが強い反面、外からの変化に対して慎重になる傾向があると言えるかもしれません。小さな村だからこそ、手に手を取り合ってみんなで進んでいかなければ立ち行かなくなります。何か村にとって大切なことを決めるときには、地域に出向いて村民の意見を少しでも多く聞き、村にとってより良い判断を下す。その繰り返しで進んできたのです。
村民との意見交換の後、村民の代表である議会とも話し合い、新庄村はどうすべきなのかを探っていきました。振り返ってみると、特に子育て世代の村民を中心に「合併したほうがいいのでは」という空気があったように思います。
村民の方々や議会と話し合いを行った末、最終決断は村長である私に託されました。そこで出した答えは、「自主自立でいこう」、つまり合併はしないというものです。「メリット論にのみ目を奪われてしまい、急いで合併号という名のバスに飛び乗る必要はないのではないか。バスは求めればいつでも停まってくれるはずだ」というのが、私が伝えた想いでした。
実は、自治体の合併は平成の大合併のときに限った話ではありません。新庄村の周囲では、村ができた明治5年以降、何度か合併の話が持ち上がっていましたが、先人たちは合併という判断をせずに村をつくり続けてきたという歴史があります。その時代の課題に対して、汗を流し、時には血を流して耐えながら、みんなでやってきたという村の歴史と伝統がある。その歴史を想うと、「メリットがある」ということだけに気を取られてしまっていいのかと疑問に思いました。新庄村宣言には、「先人たちに恥ずかしくない判断をして、これからも村として生き残っていこう」という想いもあったのです。

小さな村の大きな挑戦。
消滅可能性がついに解消
合併をせずにやっていくことに決めた新庄村は、「小さな村の大きな挑戦」を合言葉にして自主自立を目指して取り組んでいくことになりました。私が旗印としたのは、村長になったときに掲げた「村民一家族」というスローガンです。小さな村なのだから、みんなで力を合わせてつくっていこうという想いを表したもので、私の政策の根底には「村民一家族」があります。
新庄村では、マチづくりの指針として「新庄村振興計画」を進めてきました。今は、その第2期に取り組みはじめたところです。第2期では、50年、100年先も新庄村が存在するよう、未来に向かった取り組みを加速させてまいります。
第1期では、村長選挙で分断された村民が団結できるよう「村民一家族」を謳うところから施策をはじめました。そこから、詳しくは後編でお話しますが、村の中心部に福祉の拠点づくりを推進。その後、「素晴らしい村に訪問する方を増加させるために表玄関・裏玄関のある村にしよう」との方針のもと、冬期に通行止めとなる区間の通行を通年で可能にするため、野土路(のとろ)トンネルの開通に着手しました。ここは、もともと旭川の源流域で、外部とのアクセスが限られた場所だったのです。将来のことを考えると、地域そのものが優位性を持たなければなりません。そのためには、「どん詰まり」ともいえる立地のままにするのではなく、裏玄関となる場所を作って道をつなげ、どこにでも行けるようにするべきだと考えたのです。全長2kmの野土路トンネルは、通称「小倉トンネル」と呼ばれることもある、村の利便性を上げる存在となりました。
人口に関連する取り組みも行い続けてきました。10年前には消滅可能性自治体だった新庄村が、先般の人口戦略会議でそこから脱却したことが判明し、「あんなに小さな村が」と驚かせたものです。自然な社会減は仕方がありませんが、新庄村では特に若者、女性の社会増につながる努力を続けており、それが功を奏しているのだと思っています。子育てや教育に関する施策や手当は数えはじめるとキリがないくらいやっていますし、医療の無償化、給食や保育園の無償化といった取り組みも、全国に先駆けて行ってまいりました。放課後教育として、子どもたちの第3の場所づくりにも力を入れています。こうした取り組みから、将来推計の結果が好転し、消滅可能性自治体から脱却できたのです。
新庄村では、道の駅も県内で最初に作りました。基幹産業である農業を成長産業とし、農家の方々が今後も夢を持って働き、経済的に豊かになるようにという取り組みですが、若い方にも働いてもらえる場が増えるという、人口問題にもつながる取り組みになっています。
人の流入を増やす取り組みとして、地域おこし協力隊の取り組みも推進してまいりました。新庄村では離職率が少なく、定着率が高いのが特徴です。これは、ひとえに地域おこし協力隊の取り組みに中心的に関わってくださっている担当者の努力の賜物だと思っています。というのも、最初は都市部で相談会を開き、「誰でもいいよ」と来たい人であればどんな方でも受け入れる姿勢でいたんですね。すると、中には新庄村と合わない方もいて、離れてしまう方が出てきました。
今は、担当者が目的を持って「こういう方に来てほしい」とお伝えしたうえで丁寧に面接を行っており、マンツーマンの伴走支援を行い、関係ができた方にお越しいただいています。「誰彼問わず」ではなくなったことが、結果的に定着率につながっているのでしょう。

村民にもっと誇りを持ってほしい
新庄村のように小さな自治体が生き残っていくには、やはり人口減少への対策が最重要事項ではないかと思います。新庄村が合併しないという決断をした理由のひとつが、「鶏口となるも牛後となるなかれ」という言葉です。小さいものには、だからこその価値がある。人口減少時代になっていくなかで、田園回帰の流れも見られます。今、新庄村に若者が増えてきているのは、一定の魅力がある村だと彼らに評価してもらえているからでしょう。農業や林業が強いという特徴、がいせん桜通りという村の中心地をメインとした村の活性化、インバウンド効果の向上など、これからも新庄村ならではの取り組みを進め、「新庄村ならでは」の味を追求していきたいです。持続可能性のある村には、そうした地域独自の味が大切なのではないでしょうか。
がいせん桜通り沿いでは、グランドデザインを行い、空き家をサテライトオフィスやアートを活用した宿泊施設にするなど、伝統的でありながら、歩いていて楽しい「ウォーカブルなマチ」にしようと取り組みを進めています。このように、地域内の固有の資源を使い、地域内で経済循環できる村づくりが必要でしょう。資本が外にあったり流出したりすることなく、村内で経済が回れば、それだけ村民の所得につながっていきますし、雇用も生まれます。関係人口を増やそうと、村の資源である森林を活かした森林セラピーを開催するなど、これからもふんだんにいろいろな取り組みが出てくるのではないかと期待しています。
昨今は、がんばる地域を国が応援してくれる時代になりました。合併に関しては、当初言われていたメリットだけではなく、デメリットの話を聞くことも増えてきました。私は村長のキャリアに8年間のブランクがありますが、村長職を離れていた間、「やっぱり合併したほうがいい」と議論されたという話は聞いていません。合併せずにやっていくという当時の判断を、村民が是としてくださっている表れといえるのかもしれません。
これからも村として生き残るための取り組みを進めていきますが、その一方で、村民の方々にも自信や誇りをもってほしいと思っています。その誇りを外部に評価されるような形でもっと発信していただきたい、外部の人に共有していただきたいなと思っています。YouTubeで村のことを発信するなど、広報活動をもっと行っていくべきだと思っているのですが、現時点では、そうした活動を率先して担う人材が少ないので、そこを変えていくこともひとつのテーマだと捉えています。

ー おわりに ー
取材には、地域おこし協力隊の活動を担当する千葉さんもご同席くださいました。自身も村に移住してきたひとりだという千葉さんは、新庄村での地域おこし協力隊の取り組みについて、「大切なのは人の多さではなく、関係性×人数。少ない人数であっても、その方たちが確実に残り、村のプレイヤーになってくれたらうれしい」と話してくださいました。自身は期待しすぎずにやってきたからこそなじめたと言います。「思い通りにならないことも当然あり、それをむしろ楽しんでほしいし、困ったときには相談してほしい」と語ってくださいました。求人プラットフォーム「Wantedly(ウォンテッドリー)」のアカウントを自治体で持っており、ストーリー型で募集、スカウトを行っているという新庄村。地域おこし協力隊だけではなく、職員の採用もストーリー型で行い、「この村に合うか、合わないか」という相性を重視しているのだそうです。後編「ノンポリ学生から村長に」では、小倉村長が村長を志したきっかけ、これまでの歩みについて伺います。
PROFILE
小倉博俊(おぐらひろとし)
新庄村村長
1948(昭和23)年、岡山県 新庄村生まれ。福岡大学卒。大学生の頃、アルバイトとして関わったことから政治の世界に興味を持つ。大学卒業後に上京、大村襄治衆議院議員(第39代 防衛庁長官)の秘書を務める。1990(平成2)年に42歳で新庄村長となり、以後4期連続16年務める。2014(平成26)年に再選、2022(令和4)年の選挙でも選出され、再選後3期連続、現在通算7期目の任期を務める。
【主な役職】
岡山県町村会 会長
全国山村振興連盟 理事
岡山県市町村振興協会 理事
岡山県後期高齢者医療広域連合 理事
岡山県市町村職員共済組合 監事
日本赤十字岡山県支部 評議員
一般社団法人岡山中央総合情報公社 理事
新庄村社会福祉協議会 会長
真庭森林組合 理事