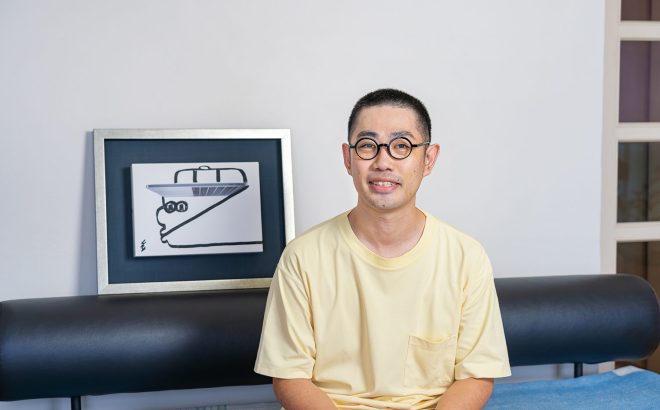若者が流出し、労働人口の減少が大きな課題となっている地域は、日本全国に数多くあります。鹿児島県奄美市も、そうした地域のひとつです。そこで2015年から『フリーランスが最も働きやすい島化計画』をはじめた奄美市。「フリーランス」が目新しかった2015年当時から、どのように取り組みを進めてきたのでしょうか。奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係の山下勝成(やましたかつしげ)さんと、同市と連携して本事業に取り組む株式会社しーま代表取締役の深田小次郎(ふかだこじろう)さんにお話を伺いました。
奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係
山下勝成さん(鹿児島県奄美市出身)
株式会社しーま代表取締役
深田小次郎さん(鹿児島県奄美市出身)
「機織りをパソコンに」
離島の課題解決を目指して
特定企業に勤めるのではなく、個人で仕事を受注して収入を得る「フリーランス」。労働人口の減少を課題とする奄美市が、企業誘致ではなくフリーランスに着目し、『フリーランスが最も働きやすい島化計画』を策定した背景には、離島ならではの課題があったのだといいます。
Q.『フリーランスが最も働きやすい島化計画』を策定した背景について教えてください。
山下:奄美市には高校卒業後の進学先が専門学校ぐらいしかなく、9割以上の若者が島外に出てしまうという現状があります。そのため、特に労働人口の減少が大きな課題となっていました。私も、本事業にご協力いただいている株式会社しーまの深田さんも、同様にかつて島外に出たうちのひとりです。
社会人になるタイミングで若者が戻りにくい理由のひとつが、ニーズに合う働き口の少なさです。そこで、多くの地域と同様に奄美市でも企業誘致に取り組みましたが、なかなかうまくいきませんでした。企業を誘致するには一定の敷地が求められるのですが、離島である奄美には、輸送コストの問題に加え、企業のニーズに応えられるだけの十分な土地がないのです。
奄美市では、こうした離島ならではの課題に対して、奄美群島12市町村が掲げる『奄美群島成長戦略ビジョン』をもとに、「農業」「観光・交流」「情報」の3つを軸に取り組みを進めてきました。そのなかで着目したのが、場所を問わない働き方ができるフリーランスです。
テクノロジーの発達により、場所を問わない働き方ができる人たちが出てきていて、そういった技術職の方の移住やUターンする事例が出てきていました。奄美市はこの「情報」を活用し、フリーランスや小規模事業者を支援することで、企業の誘致が難しい環境でも仕事の機会を生み出し、定住促進につなげられるのではと考え、「フリーランス支援窓口」を開設したのです。

(Photo:Ryo Beppu)
Q. 2015年当時、「フリーランス」はまだなじみがない存在だったのではないでしょうか。
深田:ありませんでしたね。ただ、奄美市はもともと個人で仕事をするということ自体へのイメージはしやすい土地柄ではありました。一昔前の奄美市は大島紬が基幹産業であり、機織り機が自宅にある家庭が多く、祖母や母が機織りをして子育てをするという光景はよく見られました。そのこともあって、「自宅で機織りをして生地を売っていた受発注の仕組みが、インターネット上に変わっただけで、昔の機織り機に代わるものが今のパソコンのようなもの」とたとえてフリーランスの説明をすると、自然に理解していただけたと聞きました。情景が浮かびやすく、わかりやすい説明だと思います。
なお、奄美市にはコワーキングスペース(後編参照)も設けているのですが、こちらも機織りのたとえを用いることで説明しやすいんです。集落に1、2カ所「工場(こうば)」と呼ばれる場所があり、数名で機織りをする働き方が昔から身近なものでした。フリーランスの方が集まって働ける場所として、コワーキングスペースを作りたいという話も、工場をたとえにすることですんなり理解してもらえた。開始当初に「機織りをパソコンに」と表現された方がいたことで、スムーズに計画が進みはじめたのだと思います。
Q. 本計画は、「構築期」とされる第1ステージからはじまりました。現在、2025年は第3ステージの初年だそうですね。第1ステージはどのように進んできたのでしょうか。当初の計画通り歩んでこられたのかについてもお聞きしたいです。
山下:当初から大枠の計画はあったものの、具体的な内容は都度検討し、策定し直してきました。第1ステージで目指したのは、奄美モデルの構築です。支援窓口を設置し、支援事業の核となる部分として、フリーランス寺子屋などスキルを学ぶ機会を設けました。こうした学びの場には、協定を締結した民間企業さんの力もお借りしています。
同時に、奄美市内全域でのインターネット環境の整備にも取り組みました。一部地域では、ネット環境がまだ整っていなかったんです。
深田:当時のことで覚えているのは、島外の連携企業さんにお越しいただいて開催した、一般向けの説明会ですね。70名ぐらいの参加者が集まって、熱気がむんむん漂う場でした。「フリーランス」に聞きなじみがないながらも、「畑仕事をやりながら、副業的にやってみたい」ですとか、「ネットで仕事ができる」ことに夢を持っていた方が多く集まっていたのではないかと思います。30~40代が多く、すでにフリーランスとして仕事をやっている方もいれば、「すごいことになりそうだ」と興味本位で見に来られた方もいました。
講座では、最初はライティング講座を行いました。エンジニアやデザイナーといった仕事と比べ、文章を書く仕事は挑戦するハードルが低いだろうという理由でしたね。そこから、カメラ講座など、順に講座を開いていきました。
並行して、ネット上でハンドメイド作品の販売ができるプラットフォームを運営している企業と連携し、「実際に売ってみましょう」という講座を開いていただきました。奄美市は大島紬の産地でもあり、ものづくりとの親和性が高いため、この講座も非常に盛り上がりましたね。店舗への委託販売だけではなく、ネットでも本当に売れるんだという実感にもつながったでしょうし、ハンドメイド市場の現在の盛り上がりぶりも知ることができ、励みになったことでしょう。
Q.第1ステージを進めるなかで、見えてきた課題はありましたか。
深田:「フリーランス」という働き方に対する捉え方の幅広さでしょうか。当初は「島で暮らしながらお金を稼げる新しい働き方」として、「お金を稼ぐこと」、収益性を目的に据えていたんです。具体的には、プラットフォームに登録し、そこで募集されている仕事を受注して納品し、お金をもらう。この一連の流れを体験してもらうため、まずはプラットフォームに登録してもらうところからはじめました。最も多かった案件はライティングでしたね。
進めていくなかで、奄美チームを作り、そこにまとまった量の発注をしていただけることになりました。チームで仕事を分担し、一次チェックをし、納品する。この流れで、ライターへの発注や原稿の一次チェックを担うことになったのが、私が代表を務める株式会社しーまです。フリーペーパー制作などを手掛ける会社だったことがご縁のきっかけでした。
ただ、これがなかなかに大変でしたね。当初は、インターネットを活用したフリーランス業のなかで、ライティングは「誰でもできる」という認識がありましたが、実際にはそうではありませんでした。相手の求めるクオリティに達しているものを書けるかどうかは人それぞれです。それはスキルの問題だけではなく、マインドの問題でもありました。「本当にこの仕事でフリーランスとして食べていくぞ」という気持ちの方もいれば、「ちょっとやってみたい」という気持ちの方もいる。
山下:気持ちの面でも温度差があったと。
深田:ええ。それでも、取引先には「月60本」など、決められた本数の原稿を、求められたクオリティで出さなければならないのがビジネスです。時にはチェック後に差し戻しをすることもあり、「もう嫌だ」と音を上げてしまう方もいました。単純に本数を人数で割り振ればいいという話ではなく、「この人なら任せられる」など、スキルやマインド面も見ながら橋渡しをする必要が生じ、大変だったなと思います。
山下:当時、私はまだ異動前で本事業との直接的な関わりはありませんでしたが、奄美市とはどう取り組まれていたのでしょうか。
深田:情報共有をして、相談をしながら進めていました。そもそも、どの層の人たちを支援したいのか、4象限のグラフを使いながら整理したことを覚えています。生計を立てるレベルで稼ぎたいわけではない人に対して、「もっと稼ぎましょう」と無理に引き上げるのは違うのではないか。そこで、基本的なマインドは持っているけれど、稼ぐ方法がわからないという方、スキルが足りない方を支援対象とすることを確認した記憶があります。
稼げる金額でいくと、プラットフォーム経由の仕事では思うように単価を上げていけないという問題もありました。稼ぎたい気持ちが強い方にとっては、稼げないとやる気が湧きません。であれば、プラットフォームを使わずに企業と契約すればいい。具体的に動きが強まったのは第2ステージに入ってからなのですが、自分で契約して仕事を取るようにしたことで、収入を上げられたという方も出てきました。
そして、金額だけを求めることがそもそも違うんじゃないかというのも気付きでしたね。稼ぐことさえできれば、それでいいのかと。その人にはその人の生活、島での暮らしもあるわけですから。
山下:フリーランスであれば島でも稼げるというところから、市民の方の暮らしにフォーカスするようになっていった感覚は、私のなかにもあります。奄美市が謳っているのは「どこにいてもできる仕事、ここでしかできない暮らし」です。第1ステージでの経験を経たからこそ、「仕事」だけではなく「暮らし」に目を向けるようになっていったのだなと、当初を知る深田さんのお話を聞いていてあらためて感じました。

ー おわりに ー
「時間や場所を問わず働ける働き方」としてフリーランスが注目されはじめたタイミングで、地域課題の解決に役立つとフリーランス支援事業をはじめられた奄美市。新しい働き方と思いきや、昔ながらの働き方との親和性があることにあらためて気付かされました。支援事業は「仕事」から「暮らし」に視野を広げることで、徐々に「ザ・フリーランス」のイメージに縛られない取り組み内容に変化していきます。後編では、「どこにいてもできる仕事、ここでしかできない暮らし」実現への第2ステージ、そしてこれからについて伺います。
PROFILE
フリーランスが最も働きやすい島化計画
フリーランス、小規模事業者を支援することにより、奄美市における仕事誘致、定住促進、子育て支援およびフリーランスのビジネス性向上につなげることを基本理念とする取り組み。2015年に策定され、最初の5年間を第1ステージ、2024年までの5年間を第2ステージとし、2025年4月より第3ステージに突入予定、各種施策を実施している。
山下勝成(やましたかつしげ)
奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係
鹿児島県奄美市出身。高校卒業後、山口県の大学へ進学(山口県立大学 国際文化学部国際文化学科)し、2014年4月に奄美市に入庁(紬観光課 観光・スポーツアイランド係)。総務課秘書室、紬観光課 紬特産係を経て、2020年より鹿児島県大阪事務所の観光物産課へ出向。2023年4月より、商工政策課しごと政策係に異動し、フリーランス支援、創業支援などに携わる。
深田小次郎(ふかだこじろう)
株式会社しーま代表取締役
鹿児島県奄美市笠利町須野出身。高校卒業後に上京し、東京で奄美の情報の少なさに愕然とし「島の発展は情報量に比例する」という仮説を立て、2010年にしーまブログを設立。以後奄美群島観光情報フリーペーパー「みしょらんガイド」をはじめとした情報媒体を次々に発行。奄美群島の物産を届けるECサイト、店舗運営に力を入れ、2023年にはスタートアップ支援となるシェアキッチンをオープンさせるなど、島の「困った」「こんなのあったらいいなあ」などの問題解決に取り組んでいる。
奄美市:https://www.city.amami.lg.jp/
フリーランスが最も働きやすい島化計画:https://www.amami-freelance.com/