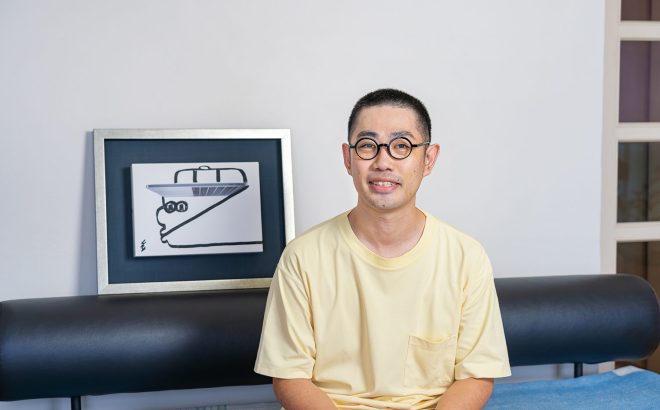2015年から『フリーランスが最も働きやすい島化計画』をはじめた鹿児島県奄美市。民間企業の力を借りながら、「会社に雇用されずに働く」体験機会を設け、島内フリーランスの育成を行いはじめました。「稼ぐ」にフォーカスしてはじめた事業は、市民の「暮らし」「人生」をも見つめるものへと広がっていきます。奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係の山下勝成(やましたかつしげ)さん、当初から同事業を支援する株式会社しーま代表取締役の深田小次郎(ふかだこじろう)さんに、第2ステージの歩み、そして未来についてお聞きしました。
奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係
山下勝成さん(鹿児島県奄美市出身)
株式会社しーま代表取締役
深田小次郎さん(鹿児島県奄美市出身)
「稼げればいい」から
「暮らしを楽しみながら働く」へ
最初の5年間を第1ステージとし、まずは奄美モデルの構築を目指した奄美市。第2ステージの「普及期」では、モデルケースの普及を目指すこと、フリーランスのコミュニティ作りの支援をテーマとして歩んできました。
Q.第2ステージでは、どのような取り組みを行われたのでしょうか。
山下:フリーランス寺子屋など、第1ステージから継続する取り組みもありつつ、フリーランスを支援する拠点作りとして、奄美市WorkStyle Lab Inno(ワークスタイルラボイノー)を作りました。コワーキングスペースやサテライトオフィスと呼ばれるような場で、フリーランスが仕事で集まれる場であり、交流や相談ができる場でもあります。しーまさんには、ここにコミュニティマネージャーとして入っていただいています。

(Photo:Ryo Beppu)
Q. Lab作りは計画策定当初からあったのでしょうか。
深田:第1ステージがはじまった当初は、まだそこまで具体的なLabの構想はなかったのではないかと思いますね。こうして拠点ができたのは非常に大きいです。第1ステージの施策の中心は講座でしたが、決まった会場がなかったことから、常に開催場所が違ったんですよ。3カ所くらいの場所を予約状況次第でぐるぐる巡っている状態で。Labができたことで、「ここでやります」という拠点ができたのは良いことだと思います。
時期的に、コワーキングスペースなどを活用する会社員の方も増えてきていましたので、交流機会や事業シナジーの創出など、いろいろなことを考えて出てきた話なのかなと。
山下:実はLabのある建物は、鹿児島県から奄美市に譲渡されたものなんです。活用方法を考えるなかで、拠点作りの話が出た。支援拠点が必要だという話と、活用すべき施設が出てきたということで、タイミング的にも非常に良かったなと思います。コミュニティマネージャーとして関わられていて感じることはありますか?
深田:コミュニティマネージャーを引き受けるにあたり、本土のコワーキングスペースを見に行きました。コワーキングスペースのコミュニティマネージャーは大変だと聞いていたので。大事にしているのは、何を軸にするのか。私たちは、フリーランス寺子屋を中心に、学ぶところからコミュニケーションが生まれると感じ、「学ぶ」と「稼ぐ」を軸として意識しています。
山下:Labでは「トーク&交流会」も開催していますね。成功しているフリーランスの方を講師としてお呼びし、10人程度と限られた人数でアットホームな雰囲気の中お話を伺っています。
深田:これまで、島で有名なイラストレーターさん、コーヒーショップを立ち上げた方など、さまざまな方が講師を務めてくださいました。職業によっては、未来のライバルに情報を話すことになるため、話しづらいところもあるだろうと思っていたのですが、意外にもかなり赤裸々に語ってくださいます。コーヒーショップのオーナーさんの回では、参加者の中に飲食をやりたいという方がいて、オープン予定の場所がコーヒーショップに近いというまさに競合関係になり得る状況だったのですが、それでもフランクに質問に答えてくださいました。
2025年度は4回の開催を予定しています。平日の昼間にもかかわらず、毎回参加者が集まっていて、オンラインでの参加希望者もいます。講師として登壇したい申し出もあり、受講者からは「参考になった」との声が寄せられています。手ごたえを感じている取り組みですね。

(提供:奄美市)
Q. 島のフリーランスの方たちの実態はいかがでしょう。変化はありましたか。
山下:第1ステージでは、ライターさん、デザイナーさんなど、クリエイター系のフリーランスの方を中心としていた部分があり、講座など支援内容もそういった方を対象として考えていました。ただ、第2ステージでは、観光ガイドさんやネイリストさんなど、クリエイティブ職とは違う個人事業をやられている方たちが、自身のビジネスを広げていくためにスキルを学びたいというニーズが掘り起こされてきて、講座内容を軌道修正していきました。
深田:ライターさんやデザイナーさん、カメラマンさんが、いわゆる「フリーランス」のイメージだったんですよね。これらの仕事は、ある仕事があり、その一部分をプロとして担うものです。そうではなく、起業して事業を手掛け、自分のビジネスを成功させるためにICT関連スキルを高めたいという人が増えてきた。ネイリストさんが、自分の仕事を広めるためにInstagram講座でSNS発信を学びたいといった具合にですね。
山下:奄美市では個人事業主や少人数の事業者も「フリーランス」と捉えているので、まさにネイリストさんたちもフリーランスの方々といえるんですよね。こうした方たちも、「フリーランス寺子屋」に参加してくださるようになった。
深田:そうですね。こうした参加者属性の変化は、ライティングスキルに求めるものの変化にもつながっています。当初のライティング講座は、SEO*ライティングのスキルを身に付けることを重視していましたが、今は自己表現やビジネス強化に役立つライティング講座へとシフトしています。
奄美市では、フリーランス支援をはじめたのとほぼ同時期に、「あまみ創業塾」という取り組みも行われています。第2ステージからは、このあまみ創業塾と連動しての取り組みもはじめました。フリーランス寺子屋も役に立っているのではないかと思います。
山下:フリーランス寺子屋は毎年開催していて、その反響や活動の成果を調査し、翌年の講座の組み立ての参考にしてきました。そうしたなかで受講者のニーズの変化に気付けたことで、講座の方向性も変わってきた気がしますね。創業塾の受講者も増えているので、事業をはじめたいという機運そのものが高まっているのかもしれません。

(提供:奄美市)
山下:このように参加者属性に変化が見られるようになりましたが、第1ステージから対象としてきたライターさんなど、いかにもフリーランスという仕事をされている方がいなくなったわけではありません。
深田:ええ。ただ、こちらも働き方に変化があります。プラットフォームを介しての仕事は手触り感がなさすぎるという意見があったのがきっかけでした。「この条件でこういう原稿を書いてください」と言われて書いたものの、その後その記事がどうなったのかわからないといったことが多く、仕事をしたというよりは、作業しただけという感覚になってしまったという方がいらっしゃったんです。請け負った仕事をこなして渡す形がいいという方もいらっしゃるとは思うのですが、奄美の方は仕事に対して手触り感を大事にされている方が多かったのかなと思います。
そこで、島の仕事をしていく形に移り変わっていきました。たとえば、私たちが作っているフリーペーパーや刊行物、パンフレットなど、島にまつわる仕事は島のフリーランスに依頼する。すると、受けてくれたフリーランスの方たちの喜びがすごく大きかったんです。「これが目指す形なんじゃないか」と思いましたね。
ただ稼げれば良いのではなく、子どもを育てながら、島暮らしを楽しみながら、島のことを発信する仕事をしてもらうことが喜びにつながるんだと。そうして、観光サイトの記事や県内のテレビ会社が発注するWeb記事などを書いてもらうなど、地元の仕事にシフトしていきました。地元の仕事には発注量というまた別の課題がありはするのですが。
※SEO
Search Engine Optimizationの略称。検索エンジン最適化を意味する言葉で、検索結果の上位に自社サイトを表示させることを目的としたライティングを「SEOライティング」と呼ぶ。
Q.フリーランスのモデルケースについてはいかがでしょうか。良いロールモデルは出てこられましたか。
深田:ハンドメイド作家さんが多数出てきています。『あまみハンドメイドマーケット』という、リアルの場で販売できるイベントがあるのですが、これが盛況で、今では奄美で有数の来場者を誇る人気イベントに成長しているんです。今年は48ブースで、当日は「こんなに奄美に人がいるのか!」と驚くほどの盛り上がりを見せます。今ではハンドメイド作家さんの即売だけではなく、ワークショップやフードブースもあるんですよ。
このイベントが良いのは、まだ自分の商品を売ったことがない人が、値付けをして売る体験の場となっていること。大体売れるので、それが自信につながるんですよ。作家さんは20代から60~70代まで幅広く、熱量の高さを感じられますよ。最初は小規模なイベントだったのですが、フリーランス寺子屋のハンドメイド講座などとも連携したことで、学んだことの「成果発表の場」としての認識も生まれました。出店作家には事前に販売目標などヒアリングして意識を高め、スタッフがアドバイスを随時行いながらサポートし、終了後は実績報告アンケートや振り返り会なども行っています。
山下:フリーランスの方の数自体、第2ステージでずいぶんと増えてきましたが、特にハンドメイド作家さんの増加は顕著ですよね。あまみハンドメイドマーケット以外でも、作家さん同士が自発的にチームを作ってイベントを企画されたりするケースも出てきました。
深田:ものづくりの段階から一緒に作ろうという流れも見られます。Labでは場作りを大切にしているので、こうした動きが自発的に生まれてくるのはうれしいです。あまみハンドメイドマーケットでは、民間企業さんのサポートを得て『あまみハンドメイド大賞」という、島の素材を使ったものなど、一定の条件を満たした作品から受賞者を表彰する授賞式も行っています。
奄美市在住の方から選ばれる奄美市賞を受賞された方は、副賞として全国の方が集まるハンドメイドマーケットへの出展が旅費付きで贈られるんです。そこで日本中の作家や作品を目の当たりにした作家さんが、その刺激を奄美に持ち帰ってきてくれ、それがまた作家さんたちへの良い影響になる。良いサイクルが生まれているのだと思います。

(提供:奄美市)
Q. 「クリエイティブ」と島の活性化についてのお考えをお聞きしたいです。
山下:奄美に限っていうと大島紬など伝統文化がありますし、島は海に囲まれているため、海洋資源など地域資源がたくさんあります。ただ、その魅力に気付ける方ばかりではないでしょう。クリエイティブな方々だからこそ、顕在化されていない島の魅力を引き出せる部分があると思いますし、そういった方々が地域の活性化にとって大きな存在となると感じます。島にクリエイティブなフリーランスの方が増えてきたことで、島内で経済を循環させられるようになったのも大きいですね。これまでは島外の方に発注したり来ていただいたりしていた仕事が、島内の方に依頼できるようになりましたので。
深田:フリーランスの方すべてがクリエイターというわけではありませんが、ものづくりの文化がある土地柄か、器用な方が多い印象があります。『フリーランスが最も働きやすい島化計画』として活動をしてきた中で、クリエイターさんたちが「こうしたらかっこいいでしょ?」みたいに表現や技術を切磋琢磨し、良い意味での競争が出てきていると感じます。そして、その根底には島を思う気持ちがある。「どうすれば島テイストを入れられるか」を試行錯誤するクリエイターたちが島の活性化に寄与する部分は大きいでしょう。
山下:支援事業をしていて思うのは、Iターンの方も多いということです。Iターンの方は学びたい意欲が高いことが多く、そういった熱量の高い方と島内の方が交わることで、双方に良い影響があるのではないかと思っています。
深田:奄美には多彩な方が多く、移住者を受け入れる土壌がある地域だと思うんです。都会的なところもあれば、ウェットな近所づきあいが色濃いところもあるなど、場所によってカラーもさまざまです。そうした多彩さも強みだと思っています。
山下:地域の中でも、特に離島に移住してくる方は、人とのつながりを大切にしながら暮らしたいという方も多いでしょう。もちろん、合う合わないはあると思いますが、人と人とのつながりを大切にする島だというところに惹かれる方が多いからこそ、定着につながっているのではないかと思います。
Q. 2025年からは第3ステージとして「定着期」への歩みがはじまります。これまでの振り返り、第3ステージへの想いをお聞かせください。
深田:「仕事」作りだと思ってはじめた取り組みが、どんどん「暮らし」「人生」へと広がっていきました。特にハンドメイド作家さんからは、「場を作ってくれてありがとうございます。人生が楽しくなりました」と感謝の言葉をいただいています。ただ仕事の形としてフリーランス支援事業を展開するのではなく、奄美にマッチした形だったからこそ、これだけの反響をいただけたのでしょう。あまみハンドメイドマーケットでは、受賞者の方が涙ながらに喜んでいたり、精神的に調子を崩されて外にも出られなくなっていた方が作品を作って受賞したりといったうれしいエピソードが数えきれないぐらいあります。島の人たちの活力を生み出すことに少しでも貢献できているのがうれしいですね。
山下:行政の職員には異動があるため、私の本事業への関わりはまだ2年です。そのなかで、深田さんたちと連携しながら進めてきました。第1フェーズで「フリーランスの収益性」にフォーカスしたところから、人それぞれのニーズの違いに気付き、一歩下がって「暮らし」「人生」に視点を移したのが第2ステージです。
第2ステージ中にはコロナ禍の影響で、イベント開催が難しいこともありましたが、着実に規模を拡大してきています。イベント当日には「もっと続いてほしい」とうれしいお言葉もいただきました。また、第2ステージの期間中にはAI技術の発達もあり、最新技術をいかに取り入れるかといった内容をフリーランス寺子屋に組み込むなど、新しい取り組みも行ってきました。
第3ステージでは、奄美で活動するフリーランスの魅力や満足度の高さ、ライフスタイルを広く知っていただける取り組みも行いたいですね。「楽しそう」と感じていただけることが、「ここでしかできない」と思っていただけることにつながると思いますので。「奄美だからこそ」を目指し、「どこにいてもできる仕事、ここでしかできない暮らし」の見える化を実現させたいです。
深田:いろいろな地域を巡っている講師の先生が、フリーランス寺子屋での講座後に「奄美の方は非常に明るいです」とおっしゃられていました。教えても「でも」とできない理由を挙げる方が多いこともあるそうなのですが、奄美ではそういった反応がほとんどなく、非常に前向きな方が多いと感じるそうです。確かに、はたから見ていても、講座後に先生の元に集まって質問するなど、みんな楽しそうなんですよね。クリエイティブは「すごい!」とびっくりしたり楽しめたりするもので、私自身もその楽しさを島中に広げたいと思っています。
地域創生の流れがあるなか、奄美市は離島として先進的な取り組みをしてきたと思います。第3ステージでは、島フリーランスという島での生活をベースにしたフリーランスの形を作っていきたいですよね。事業にはいつか終わりがくるので、この事業が終わっても奄美でフリーランスとして働きながら暮らしていけるんだと思ってもらえるようにしたいです。
山下:おっしゃる通り、自治体としての支援は永劫続くものではないため、先を見据えることは重要だと思っています。ここからは、増えてきたフリーランスの方を中心としたネットワークの支援やスキルシェアの動きができたらなと思いますね。そうした仕組みが整えば、自治体の手を離れたあともフリーランスが生まれ育ち、生活しやすい島になっていけるでしょう。
深田:「フリーランス」というと若い世代をイメージされる方も多いかもしれませんが、奄美の寺子屋には60代70代の方も参加されています。そうした方々が自然と輪に加わり、「自分も稼ごう」と楽しんでいる。この実態を見える化できたら、もっと魅力を感じていただけるようになるでしょう。楽しさが伝わり、「奄美に住みたい」と思ってもらえることで、住む人が増える。これが理想ですね。『フリーランスが最も働きやすい島化計画』は、それが実現できる事業だと思っています。

ー おわりに ー
『フリーランスが最も働きやすい島化計画』が支援しているフリーランスの方たちは、「仕事」ではなく「生業」を見つけられて活躍されている印象を受けました。「島のこの景色が創造の源泉だから」「島の人たちとの交流が刺激になるから」と感じられるものがあれば、それだけで長く住み続ける理由になるでしょう。第3ステージを終えたとき、奄美市がどのような「フリーランスが働きやすい島」になっているのか、とても楽しみです。
PROFILE
フリーランスが最も働きやすい島化計画
フリーランス、小規模事業者を支援することにより、奄美市における仕事誘致、定住促進、子育て支援およびフリーランスのビジネス性向上につなげることを基本理念とする取り組み。2015年に策定され、最初の5年間を第1ステージ、2024年までの5年間を第2ステージとし、2025年4月より第3ステージに突入予定、各種施策を実施している。
山下勝成(やましたかつしげ)
奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係
鹿児島県奄美市出身。高校卒業後、山口県の大学へ進学(山口県立大学 国際文化学部国際文化学科)し、2014年4月に奄美市に入庁(紬観光課 観光・スポーツアイランド係)。総務課秘書室、紬観光課 紬特産係を経て、2020年より鹿児島県大阪事務所の観光物産課へ出向。2023年4月より、商工政策課しごと政策係に異動し、フリーランス支援、創業支援などに携わる。
深田小次郎(ふかだこじろう)
株式会社しーま代表取締役
鹿児島県奄美市笠利町須野出身。高校卒業後に上京し、東京で奄美の情報の少なさに愕然とし「島の発展は情報量に比例する」という仮説を立て、2010年にしーまブログを設立。以後奄美群島観光情報フリーペーパー「みしょらんガイド」をはじめとした情報媒体を次々に発行。奄美群島の物産を届けるECサイト、店舗運営に力を入れ、2023年にはスタートアップ支援となるシェアキッチンをオープンさせるなど、島の「困った」「こんなのあったらいいなあ」などの問題解決に取り組んでいる。
奄美市:https://www.city.amami.lg.jp/
フリーランスが最も働きやすい島化計画:https://www.amami-freelance.com/