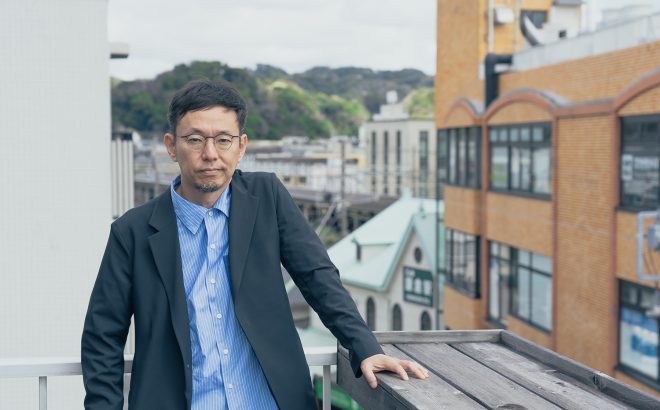「うんこミュージアム」をはじめとした面白プロデュース事業、ゲーム事業など、多種多様な事業を手掛ける面白法人カヤック(株式会社カヤック)。そのうちのひとつが、「ちいき資本主義事業」です。同事業でカヤックが提唱している地域資本主義とは何なのか、最初の実践の地である神奈川県鎌倉市での取り組みとは。カヤック代表取締役CEOの柳澤大輔(やなさわだいすけ)さんに伺いました。
経済・社会・環境
3つの資本で地域を豊かに
カヤックでは「地域資本主義」を提唱しています。2020年7月には「ちいき資本主義事業部」を設立し、事業を推進してきました。事業は5つの階層に整理していまして、その1番下に位置するのが「地域資本主義」です。地域資本主義の考え方をベースに、コミュニティや地域活性化プラットフォーム、まちづくりコンテンツ事業、地域への投資事業が積み重なっていく形ですね。

資本主義社会は、資本を増やしていくことで社会が豊かになるという理屈で成り立っているものです。僕らは、この資本主義にどっぷりと浸かりながら活動しており、その最たる存在が上場企業です。カヤックも上場しているのですが、上場企業の役目は資本主義をしっかり引っ張っていくこと、企業を成長させ、経済的な価値を伸ばしていくことで社会に貢献するというリーダー的な存在を担うことだと思っています。
しかし、世界全体が経済的な資本だけに目を向けて邁進してきた結果、地球環境など、いろいろな問題が出てきました。そのため、「ただ稼げばいいわけではなく、社会的な責任をしっかりと負いながら稼ぎましょう」というルールが増えたのです。
社会的な責任を負いながら経済活動をしなければならなくなったにもかかわらず、これまで以上に経済資本を早く増やしていこうという流れも強まっています。特にアメリカが顕著なのですが、日本でも効率的に早く経済成長させようという方向に舵を切っている。こうした全体の流れがある中では、いくら「社会的な責任を負う」というルールを企業に課したところで、世界がより良い方向にはいかないのではないか。企業が経済資本ではないものにも目を向ける必要があるのではないか。こうした想いから生まれた発想が、地域資本主義なのです。
これは別に難しい話ではなく、「マチ、地域に貢献する企業を増やしていく」、その際に「経済資本だけではなく、別の資本にも目を向けて企業がコミットしていく」というだけの話で、その別の資本を、僕たちは「地域社会資本」と「地域環境資本」としています。経済資本が悪なのではなく、経済資本だけを追うことに問題があるため、社会資本や環境資本も上手く数値化し、全体のバランスをもう少し踏まえた上で企業が躍進できるのではないかと考えているのです。
テクノロジーの進歩により、これまでは計れなかった数値も取得できるようになりました。たとえば、何十年前くらいまではどれくらい環境破壊が進んでいるのか数値で見ることはできませんでしたが、今では二酸化炭素の排出量など、いろいろなものをデータとして見ることができます。
地域社会資本での挑戦として、資本主義のモノサシであるGDPでは測れなかった幸福度を測れるのではないかという仮説を立て、コミュニティ通貨「まちのコイン」というデジタルアプリをはじめました。気になるお店に行ったり、マチのクリーン活動に参加したりすることでコインをもらえ、マチのイベントでのグッズ交換でコインを使えるなど、地域の魅力を発見し、楽しむためのコミュニティ通貨で、人とのつながりが増えることで幸せ度が上がるのではないかと取り組んできたものです。

(Photo:Hajime Kino)
5階層で行っている事業は、活動する中で見えてきたものです。ただ、その根底に地域資本主義という思想がくることだけは当初から見えていました。この思想の基に挑戦し、その内容を発信することに意味があると思っています。壮大すぎるチャレンジなので、カヤック1社だけでできるとは思っていないんです。自分たちがチャレンジしたことをしっかり公開していくことが、社会全体にとってのいろいろなヒントになればと思っています。
ちいき資本主義事業部を立ち上げて、5年ほどが経過しました。2024年の売上高が9.8億円ぐらいで着地したところ、今期の目標は15億円と、徐々に経済規模が大きくなってきていまして、事業としてきちんと成長できているといっていいでしょう。主軸事業である、地域の仕事・暮らし・体験マッチングサービス「スマウト」が、関係人口を増やす施策においてしっかり価値提供できるサービスになっているので、いいスタートを切れたとはいえるのかなと。
地域資本主義に則って考えると、経済・社会・環境資本すべてが充実し、住んでいる人たちがカヤック的にいうと「面白がれる」、つまりハッピーになれる地域づくりに貢献していくことが我々の目標です。ここに取り組むのはこれからですかね。我々は鎌倉でまず取り組みはじめたのですが、鎌倉はもともとハッピーなマチなので、僕らがハッピーにできたというよりは、「元からハッピーな地域で実験をさせてもらえた」という感じなんですよ。鎌倉での経験を糧に、ほぼどの地域も抱えている人口減など、いろいろな課題に取り組むことで、新たな成長を迎える手伝いができるかどうかは今後の挑戦ですね。
正直、課題は山積みです。ただ、コロナ禍で移住やリモートワークのハードルが下がり、人の移動について発信をしたらマチが活性化するという取り組みを進めやすくなったとは感じています。それでも、日本全体の人口減は止められません。
経済資本の軸となるのは、やはり人口なんですよね。ですから、地域にとって最も大きな課題もやはり人口減だと思っています。そこをインバウンドや観光業で補おうとしても、住んでいる人自体が少ないために、サービスを提供できる人手が足りないという課題があります。移住者や関係人口を増やす取り組みを進めている地域も見られますが、『勝ち組』ばかり人が増え、本当に必要なところは人手不足のままという状況もある。根本的な解決策は人口そのものが増える施策なのかもしれませんが、今から子どもをいきなり増やすのは難しいでしょう。では、AIを活用してこれまで3人必要だったものを1人でできるようにするのか、移民を受け入れるのか、選択肢はいろいろあるかと思いますが、地域が盛り上がるまちづくりという意味での課題は、人口が1番の課題でしょうね。
人口を増やすための取り組みとして、よく見られるのが企業誘致です。「スマウト」でユーザーをどう地域に増やしていくのかという取り組みを行ってきましたが、まだ「こうすれば企業誘致ができますよ」といえる知見は得られていません。全国的に、横展開できるような企業誘致の取り組みはないのではないかとも思っています。福岡市はスタートアップ企業が増えている印象がありますが、では東京と比べてどうなのかというと、そこまで増えているわけではありません。福岡市だからスタートアップが増えているというよりは、福岡市が住みやすいために移住者が増え、その流れでスタートアップの誘致や増加につながっている話だと思うんですね。
企業は経済合理性で動きますから、どうしても税金や助成金といった条件が大きい。そのため、より好条件があればそちらに移転してしまいます。海外では産業を特化することで同業者を集め、その結果イノベーションが起きやすくなるという事例があるため、日本でもそういう事例をつくれるといいのでしょうが、「スマウト」に関してはまだそこまでの事例はないのではないでしょうか。
地域との「関わりしろ」を重視
先ほどもお話したように、カヤックは鎌倉に拠点を設け、鎌倉のマチでさまざまな試みに挑戦してきました。
拠点を置いた2002年当時、IT企業が本社を構える場所といえば六本木や渋谷など東京のマチで、鎌倉にはIT企業はありませんでした。そのため、カヤックは異質な存在だったでしょう。当時、鎌倉を選んだのは、創業メンバー3人の通っていた大学がたまたま近く、馴染みがあったから。他の地域と比較をしたわけでもありませんでした。鎌倉の魅力をはっきり言語化できていたわけでもありません。ただ、住めば都という言葉があるように、拠点を置いて過ごすことで、地域への愛着が生まれ、見えてきた魅力がありました。
そのひとつが、多種多様な価値観を受け入れる土壌ですね。これは鎌倉だけではなく、観光客が多い地域や都会の良さだと思いますが、様々な人が常に出入りする地域は、異質な存在に比較的寛容だなと思うんです。鎌倉市に移住定住課がないのも、その表れですよね。専門の課がないということは、移住定住が特に課題ではなく、自然なことだからでしょうから。
ハレーションが特にあったわけではありませんが、とはいえIT企業として地域活動に関わっていくことは異質な状態でしたから、そこで新しい関わり方を模索しはじめたのが、5階層の下から2番目、地域密着型コミュニティ活動でした。鎌倉で僕らがはじめたのは「カマコン(KAMACON)」で、鎌倉を良くしたいと考える仲間をITで全力応援する取り組みをいろいろと行っています。こうした取り組みを10年以上続けてきたことで、どんどん地域に馴染み、受け入れていただけたのではないかと思います。
あとは、マチ全体をオフィスと捉えた取り組みも行ってきました。たとえば、「まちの保育園」や「まちの社員食堂」。いずれもカヤック社員が使えるものであり、地域の方たちにも使っていただけるものです。「まちの保育園」は、自主性を育む保育を実践されているところと組んで立ち上げたもので、カヤック以外の企業も出資してくださいました。
カヤックが大事にしているブレストのエッセンスが子どもたちに伝わったらいいなと思っていますが、カヤック色を特別に打ち出した園というわけではありません。体制を整えられ、実質的に良いものができてきているのではないかなと思っています。社員が暮らしやすくなると良いなと思いますし、地域の子育て世帯の方にも喜んでいただけると良いですよね。
「まちの社員食堂」も、ただ食堂を開けばいいという話ではなく、マチと関わるものをやっていこうと意識してやっているものなんです。

このように面白いものをつくるチャレンジを続けてきていまして、2022年8月には、カプセルトイ専門店「御成カプセル」をオープンしました。空きスペースがあり、「カプセルトイショップが面白そうだからやりたい」という社員の提案からスタートしたものなのですが、そこでただ店を開くのではなく、「せっかく地域の中にある店なのだから、マチとの関わりを何かつくろう」と考えはじめるのがカヤック流なんですね。
そこで、御成カプセルでは、販売機の1台を学生団体に提供し、自由に企画を考えて使ってもらうことにしました。売上は団体の活動費に充てられるため、学生たちも一生懸命に企画を考えるんですよね。面白い取り組みになったと思います。
このように、地域との関わりしろを意識しているのが僕らの取り組みの特徴であり、地域資本主義の思想です。こうした経済効果や社会資本、環境資本をどう増やしているのかといったところを測定できるようになったら、取り組みの価値が社会的に認められるようになるのではないかと思っています。まだちょっと測定は難しいのですが、意識しながら取り組んでいますね。
面白いことをやろうとする中で気を付けてきたのは、観光業が盛んなマチである鎌倉の特徴からズレた取り組みをしないこと。カヤックとしてはマチづくりがメインであり、観光業はメイン事業ではないのですが、地域産業が観光で成り立っている以上、観光客が減るようなマチづくりをするのは良くない。常に観光業に配慮して動くようにしています。

今は分岐点に立っている
カヤックは、エンタメ事業を主軸に収益を上げている企業です。そんな企業がマチに関わることを重視しているのが独自性であり、特徴だと思うんですね。そのため、その特徴を活かしながら、上場企業として成長していきたいと思っています。上場して10年が経った今、カヤックは「より早く」「何となく面白いのではなくしっかり成長している様」を見せなければならないフェーズにきています。特にこの2、3年は「ちゃんと成長できない企業は株式市場から退場すべき」という風潮が強まっており、これまでの10年と同じ成長ペースなら上場している意味を問われてしまうと思うんですね。
上場している以上、上場のルールに則って事業を展開することが、より社会的なインパクトを生み出し、地域資本主義を広める上でも強い説得力を持つと考えています。上場ルールの枠組みから外れたところでどれだけ発信を続けても、資本主義の中心にいる企業や投資家には響きにくいのが現状です。今のカヤックはまさに分岐点に立っていると思いますね。
鎌倉では、20年かけて地域における存在感を築いてきました。ただ、今後ほかの地域で取り組むなら、この時間はもう少し短縮できると思います。すでに地域資本主義という考え方が定まっていますし、肝となるブレーンストーミング(ブレスト)も完成していて、ブレストを通じて地域をより活性化させる方法論も確立しています。考え方は普遍的なものなので、他地域でも展開できるでしょう。ただ、一般的な事業立ち上げにおいて市場が縮小している現在、成功させることが難しいのと同様に、地域における取り組みでも、すでに困難な状況にある地域を立て直すのは容易ではないと感じています。
地域資本主義の考え方は、まずその地域に進出する企業や関わる企業が理解し、意識的に持っておいてほしいですね。たとえば、御成カプセルのように、ただ店をつくるのではなく、地域との関わりしろを持つことで、マチそのものが楽しくなると思っています。

ー おわりに ー
「地域資本主義」と聞くと、何やら小難しいもののように思えてしまうかもしれませんが、経済資本だけではなく、そこで関わる人たち(社会)や環境にも価値を置き、資本と捉えて事業に取り組むことと考えると、たちまちイメージしやすくなったのではないでしょうか。後編「新たな挑戦の地は沖縄」では、鎌倉で得た経験を活かし、現在柳澤さんが新たに取り組んでいる沖縄県での活動について伺います。
PROFILE
柳澤大輔(やなさわだいすけ)
面白法人カヤック 代表取締役CEO
琉球フットボールクラブ株式会社 代表取締役社長
1974年香港生まれ。1998年、学生時代の友人と共に面白法人カヤックを設立。鎌倉に本社を置き、ゲームアプリや広告制作などのコンテンツを数多く発信。カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル(2012年)をはじめ多数のWeb広告賞の審査員や、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議構成員(2021年〜2024年)を務める。2024年、FC琉球を運営する琉球フットボールクラブ株式会社の代表取締役に就任。沖縄県内に第2本社「面白法人カヤック沖縄本社」を設立し、FC琉球のJ2昇格を目指して挑戦中。
面白法人カヤック:https://www.kayac.com/